若手医師へのメッセージ
We're always following you.:小児内分泌学トップランナーから
-
Vol.13
鞁嶋 有紀(かわしま ゆき)
所属:島根大学医学部小児科 准教授自己紹介
島根県松江市の出身で(3才まで隠岐の島の海士町)すが、大学は富山医科薬科大学を卒業しました。卒後は、鳥取大学小児科に入局、同大学で大学院を卒業しました。2014年に42才で結婚、45歳で長女を出産後、松江市の実家の徒歩圏内に住居を移しました。2021年から島根大学医学部小児科に異動し、現職となっています。
小児内分泌学との出会い~とろすぎたから~
鳥取大学小児科に入局時、上司には、いわゆる昭和世代のスパルタ指導医が多くおり、キビキビした行動がとれず、“どやされて”いました。その為、常に自信がない状態でした。医者になって3年目、当時島根県浜田市の国立浜田病院(現 浜田医療センター)勤務時代に、同時の恩師から、おまえはとろすぎて内分泌しか無理、といわれてしまいました。今ならパワハラと言われかねませんが、当時の私はそうかもしれないなと妙に納得し、同時に 性分化疾患、汎下垂体機能低下症など多くの内分泌疾患をみる機会を頂き、楽しさを感じ内分泌を進むことに決めました。
研究との出会い~IGFシグナルとピンクレディー~
内分泌を志し、鳥取大学に帰局、翌年になんと内分泌専門の神﨑晋教授が就任されることになり、私の運命は大きくかわりました。とろい人が入る内分泌がメジャーな領域となったわけです。そして、神﨑教授から積極的に米国や欧州の学会に出席する機会を与えていただき、さらに、大学院では、IGF1受容体の遺伝子解析をテーマに与えていただきました。周囲は内心、みつからないだろうと思っていたようですが、なんと、宝くじを引くような確率で、世界で2家系目を鳥取で見つけることになりました。当時、間借りして実験していた内科の研究室に、Cell signalingのインスリンシグナルの図がはってあり、稲妻のような衝撃を受けました。小さな細胞の中の現象に感動し、夢中になりました。このような経験は、人生のうちで2回しかありません(一つ目は幼稚園のころピンクレディーを初めてみたときです)。そこからどんなにつらいことがあってもIGFシグナルのことを考えたら忘れるくらい大好きになりました。院を卒業後、神﨑教授、東京大学農学部の高橋伸一郎先生の御援助があり、ニューヨークにあるマウントサイナイ医科大学のDerek Leroith先生とShoshana Yakar先生のラボに2006年から2009年まで留学しました。Shoshana Yakar先生は4人の息子さんを育てながら300以上の論文を書いており、ものすごい勢いで仕事をされていたのに衝撃をうけました。私の中では彼女が一番のメンターとなっています。留学先では糖尿病のモデルマウスを用いた骨の病態研究、そしてIgfalsKO,Igfbp3KOマウスの間葉系幹細胞の脂肪細胞、あるいは骨芽細胞の分化の研究など多くの経験をさせていただきました。また、当時のラボで働いた糖尿病専門医師の女性のほとんどがお子さんを持ちながら医師・研究をこなしている姿にカルチャーショックをうけ、少なかった結婚願望が芽生えるようになりました。帰国後、前述のような家族をもつ道筋に至りました。

2003年米国内分泌学会(フィラデルフィア)にて神﨑晋教授と

2009年3月マウントサイナイ医科大学糖尿病&骨疾患部門DerekLeroith教授とShoshanaYakar先生、当時のラボメンバーと
鳥取大学から島根大学へ
45歳になっての育児経験は、戸惑うことが多く、日本における男女格差の問題を、育児を通して直接感じることになりました。女性医師支援に私もできるだけのことをしたいと感じ、女性が大学でポジションをとることの重要性を感じていました。また鳥取大学では藤本正伸先生を中心に多くの若手が育っていました。難波範行教授が神﨑晋教授の後就任され、後輩に道筋を譲ることも念頭に置き、思い切って、島根大学小児科准教授の公募に応募し、2021年から現職になります。それまで、いろいろな経験をしてきたつもりでしたが、大学を変わったのは本当に大きな変化でした。幸い、鬼形和道先生、小林弘典先生、和田啓介先生の小児内分泌Gの先生方、竹谷健教授、小児科医局の皆様に支えられ、島根大学でのあたらしいミッションに挑戦しつつあります。

2023年島根大学医学部小児科教室員の皆様と
最後に
ここまで書くと私のこれまでの歩みはとても変化に富んでいます。いい意味でも悪い意味でも、私は自分の気持ちに常に正直でした。その根底には小児内分泌学を愛する気持ちがいつもあったように思います。私の好きな水木しげるさんの幸福の七か条の中にこうあります。第一条:成功や栄誉や勝ち負けを目的に、ことを行ってはいけない。第二条:しないではいられないことをし続けなさい。第三条:他人との比較ではない、あくまで自分の楽しさを追及すべし。以後略 本学会員になり、20年以上たちます。これまで本学会員の皆様の暖かい気持ちに支えられて、今の私がいます。本学会は、若い人に対して愛情をもって、見守ってくださる土台があります。皆様も小児内分泌学を愛する気持ちを育て、活かし、その思いを未来につないで行くことを切に願っています(愛する気持ちに小さい大きいはありません)。私もまたその一助となりたいと考えています。
-
Vol.12
磯島 豪(いそじま つよし)
所属:国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 小児科 部長自己紹介
三重県津市の出身で、2000年に東京大学を卒業しました。東大と帝京大で1年間の研修医、茅ヶ崎市立病院で2年間の一般小児科研修を行いました。茅ヶ崎市立病院時代に、人生で初めて「10歳で発症した腸管逆回転症の1例」という症例報告を書きました。その時の小田洋一郎先生からの「境界領域は分かっていないことが多い」というお言葉は現在でも大切にしています。その後、国立成育医療センター新生児科で2年間研修し、全身管理のバランスの重要性を学んだことで、生涯にわたるバランスについて勉強しようと考えて、小児内分泌代謝を専門とすることに決めました。国立成育医療センター内分泌代謝科、東大小児科、帝京大学小児科での勤務の後に、セントビンセント医学研究所へ留学しました。帰国後に大学の先輩からのお誘いを受け、2022年より虎の門病院小児科に勤務しています。
小児内分泌代謝の臨床と研究
2005年に小児内分泌代謝の研修を成育で開始しました。堀川玲子先生のご指導を受けて内分泌代謝の診療の奥深さを感じていました。そんな折に、成育に臨床研究センターができて、臨床研究についての勉強をさせて頂く機会を得ました。研究というと細胞やマウスを使って行うものだと思っていましたが、臨床上大切なことをまとめていくことも研究になるということを、田中敏章先生、横谷進先生から教わり、とても画期的でした。2人の専門が成長学であり、特に成長曲線について勉強させて頂きました。成長曲線という基準値について知ることで、様々な臨床で用いる基準についての重要性を認識できるようになりました。
2009年に東大に戻りました。幸運なことに、同時に北中幸子先生も東大に戻って来られ、遺伝子解析や細胞実験について教わりました。北中先生からは、症例から多くのことを学ぶ重要性を教えて頂きました。特に印象深かったのは、腎臓にしか症状がないけれどもNail Patella症候群(NPS)の腎症が疑われた症例の解析です。偶然にもNPSの原因遺伝子であるLMX1Bの新規変異を同定し、機能解析をしてアメリカ腎臓学会で報告しました。驚いたことに、論文リバイス中に、フランスの研究室から巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)の家族例を集めたコホートのエクソーム解析でLMX1Bの同じ変異が同定され、機能解析なしでアメリカ腎臓学会誌に掲載されました。1人の症例から考えた可能性と世界的なコホートから得られた結果が同じであったことに驚きを感じるとともに、症例を深める大切さを実感しました。これらの結果からLMX1B関連腎症(FSGS10)の疾患概念が形成されました。
2014年:永井敏郎先生のご紹介で、韓国のサムソンメディカルセンターで成長曲線について、英語での講演を初めてさせて頂きました。

2015年:東京大学小児科内分泌代謝班メンバー: 北中先生(後列右)、筆者(後列左)、大学院生の田村先生(前列右)、実験助手の小内さん(前列左)
成長は個人のペースで
44歳の時にメルボルンにあるセントビンセント医学研究所のNatalie A Sims先生の研究室に留学をして、皮質骨の成熟についての基礎研究をしました。留学には昔から行きたいとは思っていたものの、時間だけが過ぎ40歳を超えていました。あきらめかけていましたが、ふとした事から人生最後のチャンスと44歳で頑張って留学することにしました。家族にとってもチャレンジングな経験でしたが、帰国してみて家族全員がメルボルンで過ごせて良かったと感じています。Natalieの研究室は小さな研究室ですが、骨代謝の世界ではとても有名な研究室です。留学を通じて、小さな研究室から大きな成果を出している理由を肌で感じることができました。医者の人生は、人それぞれペースが違うので、何歳になっても学ぶチャンスはあります。年を取ってからの留学では、その後の人生の選択肢が狭いという欠点はあると感じましたが、Natalieによると「60歳まで臨床をしていた先生が、退職後に研究を始めて素晴らしい結果を出している」とのことで、選択肢が狭いという考え方は、自分から選択肢を狭くしているのかもしれないとも思いました。小児内分泌学会の先生方で、留学に行ってみたいと考えている先生は、思い切って留学してみることをおすすめします。

2019年:研究所はメルボルンの中心街近くにあったため、時々街でランチをしました。写真は、研究所すぐそばのCarlton Gardensでのランチです。

2023年:第41回日本骨代謝学会学術集会ランチョンセミナーでNatalieの講演の座長をさせて頂きました。
メッセージ
気付けば若手医師へのメッセージを書くような年齢になってしまいましたが、今でも診療で不安になることは多々あります。そんな時は、これまで教わってきた先生方のお言葉を思い出したり、様々な先生のご意見をうかがったりして何とか解決しようとします。医学が日々進歩している時代なので、1人の力で全てを解決することが難しいことも多いと思っています。若手医師の先生方は、臨床においても、研究においても、自分で考える習慣を大切にしつつも、1人で全てを解決しようとせずに、多くの先生方の力を合わせることで、困難を乗り切っていくバランスが重要なのではないかと考えています。
-
Vol.11
窪田 拓生(くぼた たくお)
所属:大阪大学大学院医学系研究科 准教授自己紹介
出身は和歌山県です。和歌山の甲子園で優勝経験のある高校を卒業後(野球部には所属していません)、大阪大学医学部医学科に入学し、留学期間を除いて、ずっと大阪に住んでいます。大学時代は医学部バドミントン部に所属し、バドミントンに明け暮れていました。
研修医時代
私の時代は医学部卒業後ストレートに入局するのが普通で、1年目は大阪大学医学部附属病院小児科、2~3年目は関連病院、4年目は再び大阪大学医学部附属病院で小児科研修を行いました。この間に、学会や研究会で多くの症例発表をする機会を頂けたのは良い経験になりました。発表について「分かりました」「分かりました」と受けていたので、月に3回発表することもありました。これらの症例発表の中で、症例報告を英語で2本書けたことは私の財産の一つです。
大学院生時代
4年目の半ばに、次の進路をどうするかを考えたときに、それまでご指導いただいた先生方を思い浮かべ、元々漠然と考えていましたが、「subspecialtyを持ちたい、大学院で研究してみたい、将来は留学したい」というのがより固まってきました。内科治療などを行いながら、疾患を管理し子どもの成長を見守っていく、というのを行っていきたいと思い、腎臓・骨代謝・内分泌のグループに入りました。その直後に大薗先生が教授として赴任され、1年間の関連病院での勤務ののち、大学院に入りました。大学院では大薗先生、医局やグループの先輩のおかげでWntの共受容体Lrp6の変異マウスの骨代謝を解析する機会を頂きました。成果は主に日本骨代謝学会で発表しました。日本骨代謝学会に参加している小児科医は少数ですが、硬組織を研究対象にしている学会なので(最近は運動器全体も研究対象)、内科、整形外科、歯科、基礎などの研究者が主な参加者で、学際的な学会です。その延長で、ASBMR(American Society for Bone and Mineral Research)で発表する機会もいただきました。口演でしたので、想定質疑回答リストを作成しました。実際は、聞き取れた単語から質問を予測し、最も近い回答を答えました。著名な研究者も質問してくれましたので、研究内容に興味があるのだなと感じ、嬉しかったのを覚えています。英語は重要だなと改めて実感し、学習を続けています(なかなか上達しないのが辛いところです…)。研究の方は何とか進み、論文が受理されたときは非常に嬉しかったです。留学については、運のいいことに、論文が受理された頃に、以前に声をかけていたラボからポスドクの空きができたとの連絡がありました。幸い、そのラボにポスドクとして採用してもらえました。
ポスドク時代
留学先(米国University of California, San Francisco、Bikle教授)では骨代謝におけるIGF-1シグナルと力学的負荷の関連について、骨芽細胞特異的IGF-1受容体欠損マウスを用いてHindlimb unloading(尻尾を吊り上げて、後ろ足をどこにも接触しないようにすることによって、後ろ足を無重力のモデルとした実験)と再加重を行い、骨形成反応を検討しました。実験が慣れてきたころに、ボスの勧めでNASA関連のグラントに申請しました。採択されたのは良かったのですが、training programがあって、研究提案を英語で30分行うのは大変だったのを覚えています。原稿を読むわけにもいかないので、台湾出身の先輩にアドバイスを求めたところ、「100回読んだら覚えられるよ」と言われ、懸命に暗唱したのを思えています。 私はアメリカに留学したのですが、米国と日本の色々な違いが分かったのは貴重な経験でした。よく言われていることですが、日本を外から見られたのも良かったと思います。私が留学したラボには4人のPI(principle investigator)がいたのですが、1名がMD, PhD、1名がMD、2名がPhDのラボでした。最近は日本でもそうですが、米国ではオンとオフがはっきりしています。多くの研究者は定時に帰宅します。土曜日にラボに来ていることもまずありませんでした。でも、昼間はPI、研究員、テクニシャン、秘書とほぼ全員がモーレツに仕事をしている感じです。さらに、2名のMDのPIは比較的遅くまで仕事をしていました。言葉のハンディがある私としては、「結果を出すに人より多くの時間を研究に費やそう」と思い、研究をしていました。研究はあまり順調ではなかったので、わがままを言って留学期間を2年から3年に1年延長していただきました(上記のグラントも留学の2年目から2年間だったこともありましたが)。
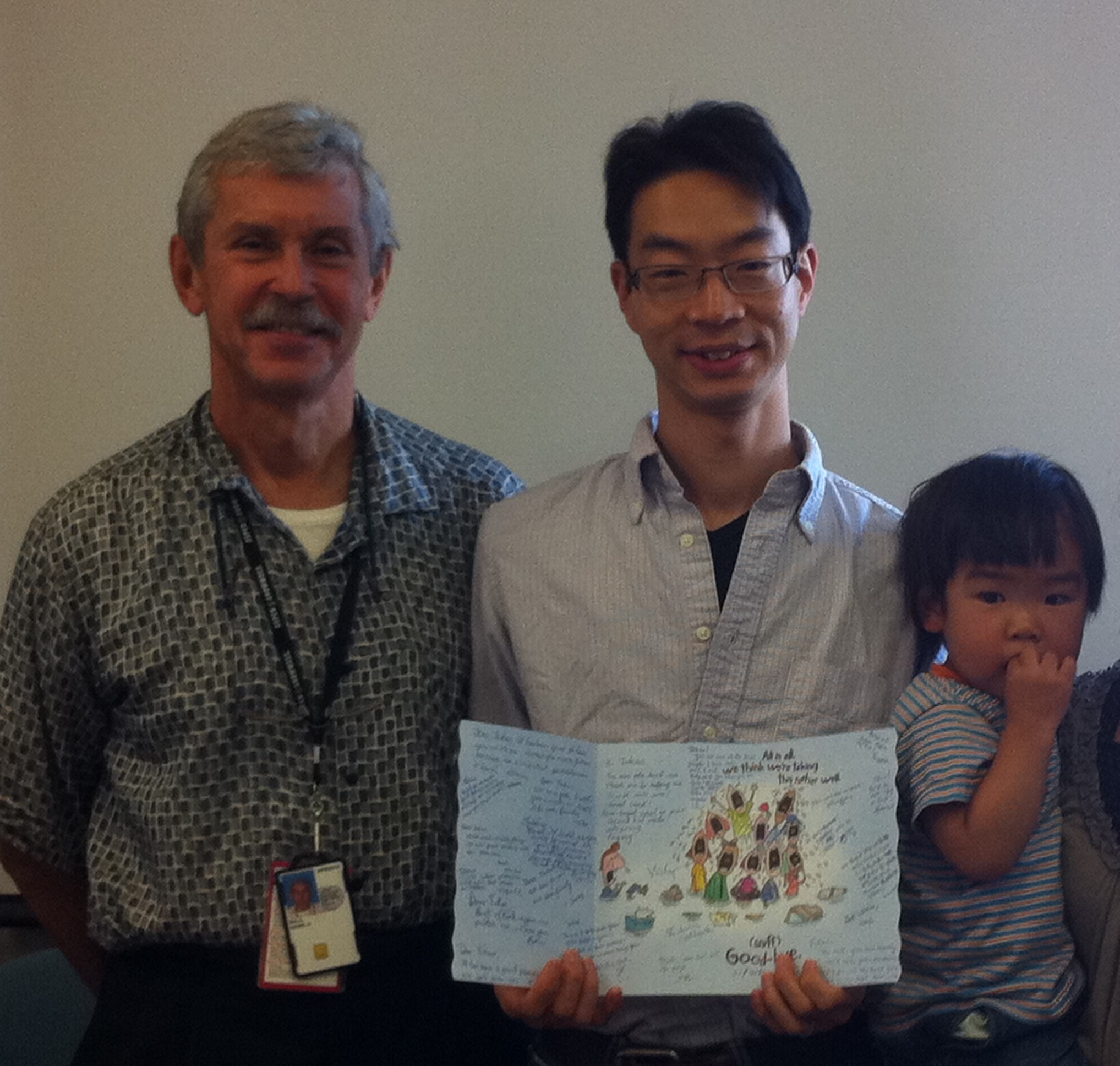
留学先のラボでのfarewell party(左がボスのBikle教授、右が長男)
大学時代
帰国後、大阪大学小児科に戻ることができ、iPS細胞やモデルマウスを用いた基礎トランスレーショナル研究は大学院生を指導しながら、臨床試験やゲノム研究、観察研究などの臨床研究はグループメンバーの協力を得ながら、主に骨疾患研究を進めています。内分泌疾患・骨疾患の診療、学生や専攻医の教育にも励んでいます。今も、ASBMRに毎年参加するのを一つの目標にしています(ESPEやENDOも行きたいのですが)。海外の学会に参加すると、国内の学会以上に刺激をもらえます。目の前の子どもをサポートしながらも、是非、世界に目を向けて、皆様の手で、小児内分泌学と小児内分泌疾患の医療を前進させてほしいと思います。
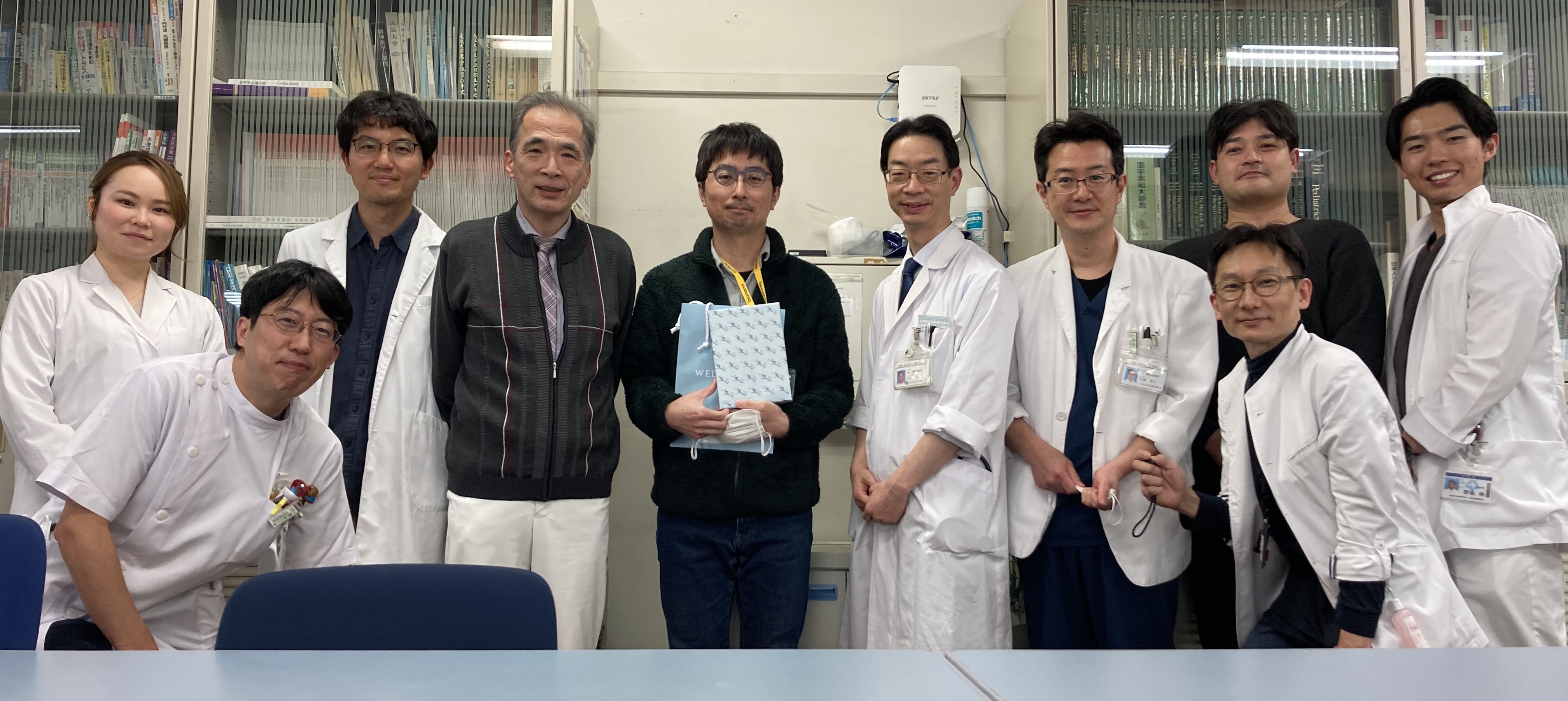
大阪大学小児科学の研究室のメンバー(少し前)
最後に
小児骨代謝研究について。骨代謝は小児内分泌学研究の中で、メジャーな領域とは言えないかもしれませんが、骨は成長が行われている、まさに“現場“であり、骨量獲得も行われており、骨は小児内分泌学の中で重要な領域の一つであると考えています。ご存知のように、生体や骨の恒常性維持に必要なカルシウム・リンは体の複数の臓器(副甲状腺、腎臓、骨など)から産生されるホルモンによって調節されています。栄養や生活習慣も関連します。一人でも多くの方が骨代謝に興味を持ってもらえることを願っています。
-
Vol.10
伊達木 澄人(だてき すみと)
所属:長崎大学医学部小児科学教室 准教授自己紹介
みなさんこんにちは、長崎大学小児科の伊達木(だてき)と言います。1975年生まれの47歳になります。生まれ育ちは長崎市の茂木という田舎町で、ビワと新鮮な魚介類が有名なところです。中学から大学まで柔道部に所属していました。長崎大学医学部を卒業後は小児科学教室に入局し、関連病院での勤務、国内・海外留学を経て、現在長崎大学病院に勤務しています。内分泌を専門分野と決めたのは、研修医時代の思い入れのある症例に出会えたことがきっかけとなっています。当時新生児だった症例を現在も外来でフォローさせていただいております。信頼関係をもって長く患者家族と付き合えることは、小児科、小児内分泌代謝分野の魅力のひとつだと思っています。

長崎大学病院 内分泌代謝班(2023)
後左から本川未都里先生、中富明子先生、川村遥先生国内留学・海外留学のすすめ
私は大学院入学とともに3年間、国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部に国内留学しました。ここでの経験、緒方勤先生、深見真紀先生、鏡雅代先生にご指導いただいたことは、リサーチマインドを持ちながら診療する基礎となっています。また、学会発表、論文作成等の情報発信のノウハウと重要性を学びました。この間、現在各方面で活躍されている先生方と知り合いになれたことも、大きな糧となっています。
海外留学については、運とタイミングがあります。留学先の伝手がなかった自分は、同じ研究分野で高名なSally Radovick教授に当時ニューヨークで開催されたIMPEで面談する機会を得て、留学に繋がりました。Johns Hopkinsの2年間では、公私とともに充実した生活を送ることができました。プライベートでは次女の出産、育児を経験でき、日米の医療の違いを学ぶいい機会となりました。昨今、学位取得を目指す医師、海外留学を希望する研究者が減っていると聞きます。臨床家としての研究活動は、学問的な探求のみならず、臨床の幅を広げることに貢献します。長い人生の中で、数年間でも違った環境で研究に集中できる環境に自分をおくことは大きな財産となるのではないでしょうか。
第14回国際内分泌学会議ICE2010で来日された
Sally Radovick教授とFredric Wondisford教授(ご主人)
緒方勤先生、深見真紀先生とともに(世田谷 砧公園にて)地方での勤務のすすめ
おそらく多くの若手の先生方は、大学病院やこども病院、各地域の中核病院で、少人数のグループの一員として内分泌の診療を切り盛りされていると思います。特に我々のような地方大学では人材不足が顕著で、留学から帰ってきたときは、1人診療班の時期もありました。また、施設によっては代謝性疾患を含め内分泌以外の分野も担当せざるを得ず、診療業務や雑用もそれだけ多くなってしまいます。若くして経験があまりない中、責任に圧し潰されそうな方も多いのではないでしょうか。しかし、地方で働くことは、地域単位で幅広い分野の診療ができるという点において、大きなメリットだと信じています。現代は、学会のおかげで教科書やガイドライン等が充実し、またその道のスペシャリストにコンサルト可能であり、ある程度全国均一な医療が提供可能です。他施設とも連携をとりながら、地方の砦として機能すること、また新しい知見を地方から全国に、全世界に発信することが十分可能です。症例は少なくとも、患者一人一人に真摯に向き合い、最善の医療、トータルケアを提供する中で、勉強させてもらうことは多々あります。臨床でも研究分野でも地方でできないような目標ができたとき、留学を検討したらよいと思います。
おかげさまで長崎にも小児内分泌の分野に興味を持ち、一緒に診療する仲間が増えてきました。皆で成長し、診療水準を維持し、継続して情報発信することが今後の目標です。その結果として小児内分泌領域に興味を持ってくれる先生方が増えてくれることを願っています。 -
Vol.9
糸永 知代(いとなが ともよ)
所属:大分大学医学部小児科 助教はじめに
このコーナーで御指名をいただいたことは驚くばかりです。当然トップランナーとは言い難いあり様ですが、トップランナーになることを目指しなさい、との叱咤激励と思い、お受けいたしました。私のような凡庸なものが、凡庸なりにどのように過ごしてきたか、ということが少しでも皆様の背中を押すお手伝いになればと思います。
自己紹介
温泉で有名な大分県で生まれ育ちました。源泉数、湧水量日本一です。高校卒業後、熊本大学医学部へと進学しました。学生時代をご存知の方は、私がいかに不真面目な学生であったかをよくご存知のことと思います。かつ、超ド級の人見知りで、自分の殻と部屋に閉じこもり狭い世界で生きていましたが、良き友人や先輩と出会うことができ、ちゃんと卒業することができました(その友人の一人が、のちに再会を果たす永松扶紗先生です)。大学卒業後は、地元大分に戻り、初期研修を経て、2010年に大分大学小児科に入局しました。入局後は、主に地域の病院、重症心身障害者施設などで勤務をしました。有名研修病院での研修と比べれば症例経験は少なく、そのことで思い悩んだ時期もありましたが、地域病院ならではの診療、保健活動や多職種と連携する機会が多くあり、小児科医としての幅を広げることができたと思います。また、この時期に症例報告の論文を書かせてもらいました。一例報告でしたが、当時の教授や指導医の先生と何十往復もやりとりし、3年くらいかかってしまいました。当時はつらかったのですが、この経験は礎となったように思います。根気強くご指導いただいた先生方には感謝してもし切れません。
なぜ小児内分泌を選んだのか
小児科スタート当初は、様々な疾患を診療できるということに最大の魅力を感じており、専門は決めていませんでした。上述のように、私は、凡庸かつ人見知りなので、相談するのも決断するのも遅く仕事にはとても時間がかかります。同期の友人がさっと仕事を終わらせるのに対して、夜遅くまで病院にいないと仕事を終わらせることができませんでした。おそらく、患者さんを目まぐるしく多く診るような病院では、知識や技術はものにならなかったと思います。そういった自分の力量や性格から、患者さんやご家族と長く付き合って関係を築けること、その中で疾患を抱えつつ生活することを手伝えること、そういった分野をじっくりやることが自分には向いていると思うようになり、内分泌分野に興味を持ちました。一つのホルモンで様々な臨床像が説明できたり、ダイナミックな病態を垣間見ることもできたり、小児科ならではの成長や思春期と直結する点も好きでした。
当時、大分大学には小児内分泌を専門にしている先生はおひとりしかいませんでした。後継者問題が生じていたこともあり、弟子入りすることにしました。そこで師匠に、どのように一人で学んできたのか伺ったところ、「とにかく勉強して、分からないことは学会や研究会で偉い先生に聞いて回った」、「だから貴方も私に聞かずにそうしなさい」と言われました(実際には多くのことを教えてくださいました!)。超ド級の人見知りには青天の霹靂...。知らない偉い先生に話しかけるなんて...。初めての症例報告の発表も師匠不在で、とんちんかんなことを連発した記憶があります。でもそのおかげで、自分なりの覚悟も芽生えたように思います。まずは九州内の研究会に参加をして、少しずつ他県の先生に話しを伺いました。次に全国学会に行ったときに、顔見知りになっていた九州の先生方の後ろについていって、沢山のことを教わりました。小児内分泌に傾倒した日々
とりあえず一人でもがいてみる、ことを続けていたとき、大分大学小児科の教授に井原健二先生が就任されました。そこから機会を得て、2016年に東京都立小児総合医療センター内分泌代・代謝科(以下、都立小児)へ国内留学させていただけることになり、2年半在籍させていただきました。国内留学先に都立小児を選んだのは、皆さんもご存知の通り、長谷川行洋先生がいらっしゃったからです。長谷川先生の著書「はじめて/たのしく学ぶ小児内分泌学」は私の座右の書でした。そして、全国からの留学者を受け入れておられ、外来診療も経験させてもらえるということで、実に多くの学びをいただきました。それまで一人だった自分が、「小児内分泌を学びたい」という同じ志を持った仲間と出会えたことは、自分の世界を広げる大切な経験となりました。他の施設との勉強会や共同研究に参加させていただく機会も頂き、いくつかの原著論文も書かせていただきました。私は、多くの仕事を瞬時に進めるようなことはできないですし、メールなどの反応もあれこれ考えて遅いですし、とにかく凡庸です。長谷川先生は、診療されるときに「患者さん本人との時間や空間を意識する」ことを大切にされていますが、私が留学中に学びを得られたのは、「小児内分泌のことを集中して学べる時間と空間」があったからだとつくづく思います。
(写真1)2018年の東京都立小児総合医療センター内分泌・代謝科メンバー。
真ん中が著者。後列一番左が留学先で再会した大学の同級生・永松先生。
これからのこと
自分が留学し小児内分泌に傾倒できる日々を頂けたのは、ひとえに、その間大分の小児医療を支え守ってくれていた先輩後輩の先生方あってのことです。そして、自分のような凡庸な人間でも、なにかに傾倒できる「時間や空間」が与えられれば、かならず得難いものが得られると信じているので、是非、後輩たちにはそのような機会が得られるようなサポートをしていきたいと思っています。もちろん、自身もまだまだ学ぶべきことが多いので、学会や研究に積極的に参加していきたいです。そして、最初の一歩にお付き合いいただいた九州の小児内分泌の先生方と臨床研究を立ち上げることが私の現在の夢の一つです。

(写真2)大分大学小児科内分泌代謝グループのメンバー
-
Vol.8
宮戸 真美(みやど まみ)
所属:国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部 上級研究員自己紹介
鹿児島県出身です。大学院修士課程まで鹿児島大学理学部で化学を専攻し、その後、熊本大学大学院医学研究科に在籍して生物を勉強しました。医師免許を有していませんので、医師の先生方のように患者さんの診療に直接関わることはありません。また、使われている薬の名前もわかりませんので、若手医師の先生方に教えてもらっています。そのため、臨床的な貢献ではなく、モデル動物や培養細胞をもちいた基礎研究の解析結果から、小児内分泌学分野の発展に貢献できると考えています。
私は、2008年から、国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部(所属当初:国立成育医療センター研究所 小児思春期発育研究部)に所属しています。これまで当研究部前部長の緒方勤先生(現 浜松医科大学特命研究教授・特定教授)と現部長の深見真紀先生(2011年に部長就任、2021年に研究所副所長就任)のもとで、小児内分泌について学んできました。現在、チームリーダーとして、医師および医師以外の若い研究者とともに研究を進めています。今回、執筆の機会を賜り、本学会のメンバーが医師だけではないことを、若手医師の先生方にも知っていただく良い機会だと思いました。
(写真1)筆者
日本小児内分泌学会に参加しての気付き
2009年から会員(2019年から評議員)として、本学会活動に参加しています。本学会に初めて参加したとき、どの演題においても質疑応答が非常に活発に行われており、この学会の先生方は皆凄いなぁ~という強烈な印象が残ったことを今でも覚えています。とくに受賞演題選考セッションでの質疑応答時の熱気には毎年圧倒されています。
また、本学会では、質問するためにマイクに出来るだけ近い席を取ることが大事であることも学びました。私には臨床に関する質問はほぼ出来ませんが、マイク近くに座って違う視点からの質問(あまりにも的外れのため、ご迷惑をおかけしているかもしれません)をするようにしています。大きな会場で質問することは、勇気と意気込みが必要(実際、いつも心臓バクバクです)で、突然出来るようになるものではありません。そのため当研究部では、ラボカンファレンスで必ず一つは質問あるいはコメントをすることから始めましょうと、たびたび話題にしています。何かを発言しようと思っているか否かで、発表を聞く真剣さは全然違ってくると思います。若い先生方は、明日からのラボカンファレンスでぜひ毎回何かしらの発言をしてみてください。毎回一言を続けていくと、発言することへのプレッシャー(?)に少しずつ慣れ、大きな学会場でも発言できるようになります。実際、学会場で発言している人の顔を見ると、当研究部の関係者がとっても多いものです。対面に戻った際には、マイク近くの席に座って発言の機会を競い合い、本学会を盛り上げていきましょう。
(写真2)第43回日本小児内分泌学会学術集会での優秀演題賞受賞時(2009年10月、於 栃木)。
筆者(左)と横谷進先生(右)。メッセージ
分子内分泌研究部では、成育医療(生殖と成長に関するライフサイクルに関する医療)に含まれる胎児期、小児期、成人期に発症する内分泌疾患およびそれらに関連する奇形症候群を含む疾患などにも注目しています。国内外の施設の先生方からさまざまな疾患の患者さんの検体をお送りいただき、継続的に検体を集積しています。現在では1万を優に超える検体を臨床的および分子遺伝学的手法をもちいて解析し、新規疾患発症遺伝子の発見、疾患成立機序の解明を目指しています。これらの解析に関して、臨床医および基礎研究者の非常に多くの先生方と共同研究を行っています。
十数年、当研究部に在籍しています。その間、たくさんの若手医師の先生方が、大学院生あるいは研究員という形で全国各地から当研究部に来られました。現在も多くの先生がいらっしゃいます。振り返ると、学生実習以来、久しぶりにピペットマンを握ったという先生も多々おられました。それらの先生方は短期集中で基礎研究を進めて得られた結果を論文化して、臨床の場に戻られていきます。その後、小児内分泌の分野をはじめ医療の現場で大変活躍されています。当研究部では、部長の深見先生を中心に、味わい深いメンバー構成(4チームあります)で日々研究を続けています。小児内分泌学分野における新たな知見の獲得に向けて一緒に研究したい方を募集しています。
(写真3)深見先生副所長就任お祝いの記念写真(2021年6月、於 成育)。
深見真紀先生(左前)、筆者(真ん中)と分子内分泌研究部の先生方。 -
Vol.7
池側 研人(いけがわ けんと)
所属:東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科はじめに
数々の著名な先生方が、とても参考になるご自身の経験を示してくださっている中で、小児内分泌の世界に入って2年半の私が、執筆の機会を頂くことになり、身に余る大役と感じています。私は、現在、都立小児総合医療センターで内分泌・代謝科と共に臨床試験科にも所属しており、多くの若手小児内分泌科医がたどるキャリアとは少し異なる道をたどっておりますので、これから小児内分泌科医を目指す、さらに若い世代の参考になることを願い、この文章を書きます。
小児内分泌科を専門に決めるまで
私は静岡県の浜松市で育ち、2014年に名古屋市立大学を卒業しました。その後、聖隷浜松病院で2年間の初期研修を行い、2016年から東京都立小児総合医療センターで小児科としての後期研修を始めました。
当院の小児科レジデント研修では、他科をローテートする機会があり、2017年(小児科2年目)に内分泌・代謝科を2ヶ月間ローテート致しました。この2ヶ月間のローテートの間、初発の1型糖尿病患者さんの管理や、外来初診の対応を主治医として関わらせて頂く機会を頂きました。その時、糸永知代先生(現 大分大学所属)に丁寧にご指導頂き、さらに長谷川行洋先生からも直接たくさんのご指導を頂きました。この2ヶ月の間、小児内分泌の学問としての面白さに触れ、長谷川先生を始めとした都立小児で働く先生方の人柄、教育に対する姿勢に感銘を受け、2019年4月から都立小児内分泌・代謝科で働かせて頂くことになりました。小児内分泌科研修を始めて
当院の内分泌・代謝科で2年半働き、とても充実した日々を送ることができ、本当にこの環境で働くことができて良かったと思っております。ここで少し当院の研修の特徴について紹介させて頂きたいと思います。
まず1つ目の特徴は、豊富な症例を経験できることです。小児病院という特性から、毎日複数の院内コンサルトがあり、その内容も多様です。また、当院の医療圏には、東京都多摩地域の小児52万人が住んでおり、長谷川先生が長い年月をかけて築いてこられた地域医療との関係も強いため、他施設から数多くの紹介を頂きます。研修1年目から指導を受けながら、初診患者の診療に直接的に関与することができます。個人的には、現在までの2年半の間に初診、再診、他科からからのコンサルトを含めて約500例の患者さんを診療させて頂き、多くの経験を得ることができました。
共に切磋琢磨できる若手・中堅医師が多いのも当院の研修の大きな特徴です。現在、北海道から沖縄まで日本全国から集まった13名(うち4名は外来のみ)の若手・中堅の医師が、当院で共に学んでいます。日々の診療はもちろん、カンファレンスや勉強会では活発な議論が行われるため、多くの学びが得られます。このような素晴らしい仲間を得られたことは、私の一生の財産です。
最後に長谷川先生の教育を受けられることが、当院の研修の最大の特徴だと思います。長谷川先生の素晴らしい人柄、豊富な臨床的知識は多くの小児内分泌科医が知るところかと思いますが、さらに、教育に対して非常に熱心です。毎日のカンファレンスでは必ず学びになる新しい知識を教えて下さります。その内容は、小児内分泌の歴史的な内容や最新の知見、ご自身の経験など多岐にわたり、多くの刺激が得られます。さらに1対1での教育の機会も多く設けて頂けます。私が小児内分泌科医になったばかりの最初の1年間は、1-2週間に1度、必ず対面の時間を作って頂き、症例や研究に関する相談にのって頂きました。いまでも、われわれ若手に定期的に声をかけ、時間を作ってくださいます。
(写真)東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科メンバー13名と見学者2名
(前列中央が長谷川行洋先生。後列右端が筆者、左端の2名が見学者)臨床研究について
2019年4月から現在まで、私は当院の臨床試験科も兼務させて頂いております。臨床試験科の森川和彦先生のもとで、臨床研究や統計について学ぶ機会を得ながら、実際の臨床研究、臨床試験に携わっております。臨床試験科としては、新型コロナウイルスに対するワクチンの抗体価・副反応調査、神経因性膀胱に対するボツリヌス毒素の安全性に関する先進医療、マイコプラズマ肺炎に対するステロイドの有効性に関するRCTなどに主に関わっています。内分泌・代謝科としても、Turner女性の骨密度調査、11-ketotestosteroneの由来に関する研究、腎性尿崩症に対するDDAVPの安全性・有効性に関する研究、XLHに関する研究などを現在進めております。臨床研究を行うためには文献を検索することが必要で、そこから多くの学びが得られます。さらに多くの症例を扱う施設として、臨床研究からエビデンスを創出していくことは社会的に重要な責務だと感じています。
今後について
現在31歳と若手であり、まだ30年以上の医師人生が残されています。まずは、小児内分泌学、臨床研究について学び、幅広いことにチャレンジしていきたいと思います。その上で、質の高い臨床研究を行い、日本から世界に発信して行きたいと思っています。小児内分泌の分野では多くの稀少疾患を取り扱いますので、多機関共同研究や学会主導の研究など小児内分泌科医が一致団結して行う研究が今後さらに増えていくことが必要であり、そこに自分が関与し続けたいと思います。
-
Vol.6
川井 正信(かわい まさのぶ)
所属:大阪母子医療センター研究所 骨発育疾患研究部門/消化器内分泌科 主任研究員自己紹介
出身は大阪です。大阪北部の箕面市というところにずっと住んでいます。箕面市にはミスタードーナツの一号店があります。あと野生のサルがたくさんいて、きれいな滝もあります。大阪に来られた際は、ぜひ箕面大滝に足をお運びください。さて、私は1998年に大阪大学医学部を卒業しました。大学病院、市民病院で4年間研修したあと、2002年に大阪府立母子保健センター(母子センター)第一内科(現 消化器・内分泌科)で勉強し、2003年より大阪大学医学部小児科で大学院生となりました。2008年にアメリカのメインメディカルセンター研究所に留学し、2010年より現職です。
研修医時代
大阪大学医学部付属病院の14階にスカイレストランというレストランがあります。学生時代のポリクリの時に、担当していた教官がそこに昼食に連れて行ってくださりました。いつもより少し豪華な昼食とともに、その先生が非常に楽しそうに留学中の思い出を語っておられたのが印象的で、その時に留学をしてみたいなと思ったことを覚えています。
1年目は同期と共に大阪大学医学部附属病院小児科での研修でした。2年目は別々の市中病院に赴任するのですが、いくつかの候補病院を提示され、同期で相談して決めるという形でした。皆であれやこれやと議論するのですが、その際、先輩の先生に「場所じゃないよ。自分自身だよ。」と言われました。ずっと、その言葉を思い出しながら、これまでやってきています。
2年目は市民病院で楽しく過ごしていたのですが、先輩医師の中に大学院を卒業したての先生方がおられ、いろいろとお話をするうちにやはり研究をやってみたいと思うようになりました。残念ながら、“このような患者と出会い、研究をしたくなった”というような過去はありません。しかし、その時に、“大学院に進んで研究を行うには、やはり英会話力と論文を書く力が必要”と思い、英会話CDを買いポータブルCDプレーヤーで聞き始めました。英語で論文を書く機会はしばらくなかったのですが、5年目に母子センターの位田忍先生のもとで研修していたときに、英文論文を2本書く機会を得ることができました。実は2本とも小児内分泌学の論文ではなく、小児消化器病学の論文なのですが。初めてアメリカでの国際学会に参加したのもこの時です。DDW(Digestive Disease Week)と呼ばれる消化器病関連の非常に大きな学会で、前述の論文のテーマを発表しました。幸か不幸か、口演に採用されました。そのころは、母子センターのすぐそばにある英会話学校に駅前留学していたのですが、何の役にもたたず、落ち込んだことを覚えています。その時の座長の先生がイタリア系の先生だったのですが、「私もこの国では外国人であり、言葉のことでは苦労しているよ。」と言っていただき慰められました。座長をされるような先生でも苦労するのだから、1年弱駅前留学しただけの僕が苦労するのは当然と思い、その後も英語を聞き続け、アメリカ留学をするまで6年間駅前留学を継続しました。20代後半から30代
2003年、大阪大学小児科で大学院生になりました。大薗恵一先生が教授に就任されて2年目くらいの頃だったでしょうか。成長ホルモンやWntシグナルの脂肪細胞分化における役割に関する研究を行い、学位を取得しました。家族の都合もあり、学位取得後の留学は半ばあきらめていたのですが、第二子の誕生と育休期間延長の法改正(?)があったことが重なり、家族で留学することができました。大薗先生と相談し、骨代謝・脂肪細胞代謝を中心に研究をされているClifford J Rosen先生のところに留学することになりました。Rosen先生が出した留学の条件の1つが“それなりに英語ができること“であり、2007年にハワイで行われたアメリカ骨代謝学会を利用して、学位論文を発表する形式でインタビューを受けることになりました。発表が終わった後、道上敏美先生から、「今の発表なら大丈夫そうだね。」と言われたのを覚えています。6年間の駅前留学の効果でしょうか?
留学場所はアメリカのメイン州のメインメディカルセンター研究所というところです。メイン州のBar Harborという街には、実験ネズミで有名なJackson研究所があります。Rosen先生は臨床をしながら、Jackson研究所で基礎研究を行っていました。しかし、基礎研究に専念するためにラボをメインメディカルセンター研究所に引っ越し、ちょうどそのタイミングで私が留学しました。留学当時のラボは、Rosen先生・テクニシャン・私、そしてノックアウトマウスの構成でした。実験するのが私だけだったので、すべての研究計画に関わり、3報の原著論文を執筆することができました。また、Rosen先生には数多くの総説依頼が舞い込んできており、留学早々に「書く?」と聞かれて、英文総説など書いたことはなかったのですが、「もちろん」と答え、必死に書いたことを覚えています。その結果、その後も数多くの英文総説を書く機会をいただき良い経験になりました。Rosen先生は頻繁にゲストを招き研究所内で講演会を行っていました。その時には必ずラボミーティングを行ったのですが、私しか実験をしていないので、毎回発表をしていました。さらに、アメリカ内分泌学会やアメリカ骨代謝学会をはじめ、何度も口演する機会を得ました。最初はラボの小ささには少しびっくりし不安もありましたが、逆に多くの機会を得ることができ、今では良かったと思っています。私が帰国するころにはラボの人数もだいぶんも増えており(写真1)、留学時期が遅れていれば、このように多くの機会を得ることはなかったでしょう。

(写真1)留学時代の写真。前列左から二人目がRosen先生。一番右が筆者。
筆者が帰国する頃には、もっと人数が増えていました。
Rosen先生からはStable Jobを用意するからアメリカに残らないかと誘われましたが、道上先生から母子センター研究所で研究を継続する機会をいただけたこともあり、2010年に帰国しました。帰国後5年間は、バイトも一切せず、患者を一人もみることなく基礎研究を行いました。私が研究医(臨床研究医であれ、基礎研究医であれ)にとって一番大切と考えていることは、“自分でテーマを見つけ、自分でそれにアプローチし、そして自分で結果を論文にまとめること”です。簡単に言えば、“筆頭かつ責任著者として論文を書く”ということです。この機会を30台半ばから後半にかけて得ることができたのは、本当に良かったと思います。40歳をこえて
当時、母子センター消化器・内分泌科の部長であった位田先生が2017年の日本小児内分泌学会(写真2)を主宰することになり、気軽な感じで「手伝ってね。」と言われました。同じころ、「もうすぐ定年だから内分泌の患者を引き継いでね。」とも言われ、患者を診るようになりました。リハビリ期間を経て外来を持つようになり、自身の色々な変化に気づきました。点滴の際に針先がよく見えなかったことには大変驚きましたが、一番感じたことは、昔とは明らかに違う目で患者を診ることができているということでした。そこで、患者を診て疑問に思うことを臨床的に調べ、論文としてまとめていくことにしました。論文を書くためには、勉強をする必要があります。そうすると、その分野に関する理解が深まり、患者さんに還元できることがどんどん増えていくことを実感しました。研究を続けてきて良かったと思えた瞬間でもありました。今は、(僕よりは)若い先生方とデータをまとめ、母子センターから発信できることが楽しみの1つであります。もちろん、基礎研究でも意義ある結果を出していきたいと思っています。

(写真2)第51回日本小児内分泌学会最終日の集合写真。
多くの先生方にご参加いただき、どうもありがとうございました。
さいごに研究は臨床研究も基礎研究も等価であると思います。どんな形でも、たとえ症例報告であっても、医学に貢献できることは、とてもやりがいのあることと思っています。また、研究を一生懸命に行った時間は、その後の診療にも大きく役立つと信じています。
-
Vol.5
鈴木 潤一(すずき じゅんいち)
所属:日本大学医学部小児科学系小児科学分野 助教自己紹介
日本大学の鈴木潤一と申します。出身は福島県で日本大学を平成14年に卒業し、同年に日本大学小児科に入局しました。2年間の小児科での研修を終えた後に、国立病院機構甲府病院へ2年間出向し、その後大学へ戻り内分泌・糖尿病の臨床に携わっています。
小児内分泌を専門としようとしたのは、単一の臓器だけではなく全身にかかわる内分泌や免疫を中心とした学問を勉強したいと漠然と考えたことと、学生時代に小児糖尿病サマーキャンプに参加して、1型糖尿病の診療に興味を持ったことがその理由です。学生のころからご指導いただいた浦上達彦先生に小児科入局後も熱心にご指導をうけ、日本大学小児科の内分泌・糖尿病グループでの診療・研究に携わせていただき、現在に至っております。
現在は大学病院および関連病院の内分泌・糖尿病専門外来を担当しており、約200名の内分泌・糖尿病の患者さんの診療を行っております。
研修医時代に小児科学会や小児科学東京都地方会などでは、症例報告等の発表はさせていただいたのですが、私が小児内分泌学会で初めて発表したのは、小児1型糖尿病年少例における持続皮下インスリン注入療法(CSII)の有効性と安全性についてでした。その後も臨床研究として小児1型糖尿病における膵島関連自己抗体の検出率、抗体価についての検討や小児糖尿病患者に対する持続血糖モニター(CGM)の有用性など、主に1型糖尿病の臨床研究をする機会をいただきました。現在も小児糖尿病における臨床研究として、インスリン治療および血糖管理の最適化、インスリンや経口血糖降下薬についての臨床研究、重症低血糖や糖尿病性ケトアシドーシスといった急性合併症についての臨床研究などを行っております。
国際学会にも多く参加する機会をいただき、特に国際小児思春期糖尿病学会(ISPAD)では学会発表だけではなく、様々な国で糖尿病診療を行っている若手医師が参加するISPAD Science Schoolに2009年に参加する機会をいただきました。Science Schoolでは診療や研究について世界のオピニオンリーダーの先生方の講義を受けることができだけではなく、 自分と同じような立場の他国医師と症例を通じてのディスカッションを行うなど交流を深め、様々な国の糖尿病診療の状況を知ることができました。
2009年ISPAD Science Schoolにて(右下が筆者)
近年では、学会や研究会の運営にかかわる機会を多くいただき、
第52回日本小児内分泌学会では事務局を担当させていただきました。
第52回日本小児内分泌学会学術集会にて(下段中央が浦上達彦先生、中央右が筆者)
診療面では、先にも述べましたが多くの内分泌・糖尿病の患者さんの診療を行っております。その中で常々感じているのは、診療の多くは医療スタッフや同じ内分泌・糖尿病グループの医師との協力のもとに成り立っておりチームで診療を行うことが非常に大切だということです。多くのスタッフが関わることで多面的、客観的に診療を行えることと、患者さん自身にも治療、管理を行うチーム診療の担い手であることを理解していただき、チーム診療の輪に加わっていただくことで、より質の高い診療が行えることが実感できています。
学生時代から参加していた小児糖尿病サマーキャンプでは、私たち医療者にとってもチーム医療を医療機関以外で実践する貴重な機会であり、現在は責任者としてキャンプを開催、運営する立場になりましたが、多くの若手小児科医、医療スタッフや学生に小児糖尿病サマーキャンプへ是非参加していただきたいと思っています。
小児糖尿病サマーキャンプにて(右端が筆者)
メッセージ2021年はインスリンが発見されてちょうど100年がたちます。インスリンが発見されるまでは、発症後まもなく死に至る疾患で不治の病とされた1型糖尿病の治療は、インスリンの発見から劇的に進歩を遂げ、現在では健常な人と変わらない寿命を全うすることが治療目標となっています。この100年の間には1型糖尿病の病態解明や検査技術の進歩、治療および管理方法の進歩がなされてきましたが、まだ現在の医学では1型糖尿病は完治できる疾患ではありません。1型糖尿病に限らず、小児内分泌領域の患者さんの予後やQOLを改善するために、私たちは少しでもそのお役に立てるよう診療や研究で努力していく必要があります。小児内分泌の領域に興味を持っている若手の先生方と一緒に、これからの小児内分泌医療の向上に尽力したいと思います。
-
Vol.4
森川 俊太郎(もりかわ しゅんたろう)
所属:Washington University in St. Louis(北海道大学小児科より留学中)幸せな悩み
 「このまま小児科の一般臨床だけを続けていて本当によいのだろうか?」という考えが頭に浮かんだ瞬間のことは鮮明に覚えています。卒業して6年目の秋、後期研修中だった病院の夜の医局でサマリーを書いている時でした。「もっと専門的な知識を得てたくさんの方々の役に立てるようになりたい」と言えば聞こえはいいのでしょうが、いま振り返ってみると溜まったサマリーからの逃避とも考えられます。とにかく、小児科医としての太い「軸」が必要と感じました。
「このまま小児科の一般臨床だけを続けていて本当によいのだろうか?」という考えが頭に浮かんだ瞬間のことは鮮明に覚えています。卒業して6年目の秋、後期研修中だった病院の夜の医局でサマリーを書いている時でした。「もっと専門的な知識を得てたくさんの方々の役に立てるようになりたい」と言えば聞こえはいいのでしょうが、いま振り返ってみると溜まったサマリーからの逃避とも考えられます。とにかく、小児科医としての太い「軸」が必要と感じました。
当時、主治医として担当していたベビーを通じて、全身の臓器をドラマチックに制御する内分泌の世界に魅力を感じ初めていたこともあり、大学院に進学しました。大学院ですぐに実感したのは、「分かっていること」と「分からないこと」の境界線は意外とすぐそこにある、ということでした。ただ、この境界線がどこにあるのかを見極めるには相当な勉強が必要であることも体感しました。小児内分泌は、臨床と基礎の距離が近い分野のひとつです。小児内分泌の臨床では、「成長」という子どもにとって最も大切な部分に医師として関わることができます。また、自分でピペットを動かす環境があれば、臨床だけでは分からない部分に(少しずつ)分入っていけるのも大きな魅力です。
臨床の場面で抱いた疑問に、どうにか自分で答えを出せるような知識と経験が必要と感じ、現在は留学先で基礎の勉強をしています。サイエンスの厳しさを前にして、これまでとは違う悩みに事欠きませんが、たくさんの方々に出会い、人生の価値観がひっくり返りそうな経験をしています。でも、そろそろ、「このまま基礎だけを続けていて本当によいのだろうか?」と思い始めるのでしょうか。
どこかでいつか同じ気持ちになるかもしれない後輩の先生方、お互い悩みは尽きそうにありませんが、私は結構楽しんでいます。
-
Vol.3
藤澤 泰子(ふじさわ やすこ)
所属:浜松医科大学医学部 小児科 講師自己紹介:
 出身は岐阜県の飛騨古川です。観光で有名な高山市より北に約15kmに位置します。さらに北に上がると、ニュートリノ観察装置であるスーパーカミオカンデのある神岡町があります。静かな小さな田舎町の古川ですが、2016年の大ヒット映画「君の名は。」の舞台となったことで有名になりました。高校は斐太高校。これもわかる年代の人にはわかるドラマ「白線流し」のモデルになった学校です。
出身は岐阜県の飛騨古川です。観光で有名な高山市より北に約15kmに位置します。さらに北に上がると、ニュートリノ観察装置であるスーパーカミオカンデのある神岡町があります。静かな小さな田舎町の古川ですが、2016年の大ヒット映画「君の名は。」の舞台となったことで有名になりました。高校は斐太高校。これもわかる年代の人にはわかるドラマ「白線流し」のモデルになった学校です。
平成9年に浜松医科大学医学部医学科を卒業し同大学小児科に入局し、小児科研修をスタートしました。最初の指導医が内分泌グループ所属であったこともあり、自然とサブスペシャリティーは内分泌となりました。4年間の小児科一般診療を経て(大学病院や関連病院)卒後5年目に浜松医大大学院に入学。DOHaD(Developmental Origin of Health and Deasease)仮説の前身ともいえる、成人病胎児期起源仮説(胎児プログラミング)に着目した研究を行いました。学位取得後はカリフォルニア大学デービス校にて博士研究員(ポスドク)として2年間の研究生活を送りました。帰国後は浜松医大小児科にて内分泌を中心とした臨床と動物実験を中心とした研究を行なっています。現在学内では主な役割は、小児病棟医長・リスクマネージャーという小児科での役割に加えて、浜松医科大学女性医師支援センターの委員も兼任しております。
研究について
臨床の仕事が大好きで当直救急NICUガッツで乗り切る、というthe小児科医でしたので、まさか基礎研究にハマっていくなんて思ってもみませんでしたた。大学院に進んだのもなんとなく、です。当時の教授大関武彦先生と研究指導責任者の中川祐一先生から与えられたテーマが「胎児プログラミング仮説の発展」です。「胎児プログラミング仮説」とは、1980年代の「低出生体重児は成人期にいわゆる生活習慣病を発症するリスクが高い」という疫学調査をもとにした「胎児期の環境は成長後の疾病発症リスクに関与する」という考えです。これを発展させ、糖尿病母体から出生した児も生活習慣病を発症しやすいことに注目した研究を行いました。ラットを使った実験にてグルココルチコイド活性の調節酵素である11bHSD1/2の発現変動との関連を明らかにして報告しました。大学院を卒業して2年後、主人がカリフォルニア大学デービス校でのポスドクのポストを得て渡米することになりました。私も同じ大学内の大学院のテーマを発展させた研究ができるいくつかの研究室にアプライしましたが、受け入れてくれるラボはなく、J2ビザ(J1ビザ=研究者に発行されるビザ所有者の配偶者や子供に発行されるビザ)にて渡米しました。渡米後紆余曲折はありましたが幸運にも受け入れてくれるラボがあり、大学院のテーマとは全く異なるミトコンドリアと酸化ストレス研究を開始しました。この時点で2歳になる子供を連れての留学でしたので、長男は渡米直後から現地の保育園に通うことになりました。言葉はもちろん英語のみ。初日は寂しく不安だったのでしょう、お弁当を全部残して帰って来ましたが、翌日は半分、翌々日には完食、とあっというまに順応していきました。2年間という短い時間でしたが、アメリカでの研究生活はなにものにも代えがたい貴重な経験でした。途中で第2子も産まれ、途中で、毒素学の権威であるProfessor Fumio Matsumuraのラボに転ラボし、ダイオキシンレセプターとアポトーシスを研究しました(毒素学の権威。結局アメリカでも筆頭で2本、共著で3本の論文という成果を出すことができました。帰国後は、現在の緒方勤教授のもとでレアな症例に対して分子遺伝学的解析や分子生物学的解析を行い報告してきました。現在はDOHaD理論の発展として胎児期の環境と男性性分化異常症や男性生殖器障害発症との関与を基礎的手法にて明らかにする研究を進めています。かなり発展性のあるテーマだと自負しています。
研究は難しそう、と思わないで、躊躇することなく飛び込んでみてください。子育て中など時間の制約を感じている先生方チャンスです。子育てと両立している女性研究者が世界中で活躍しています。

静岡県内の先生たちとWebカンファ。膝を突き合わせた議論ができない寂しさはありますが、
遠方の先生とのディスカッションが可能に。
小児科内分泌代謝グループ
緒方勤教授(前列左端)の後ろが筆者、
学内共同研究グループ医科学講座 才津浩智教授(前列右側)
家族のこと
5人家族です。主人(呼吸器内科医、浜松医大勤務)、男子3人(高校1年生、小学6年生、小学3年生)です。1人目は大学院卒業間際に出産、2人ははアメリカで生まれましたのでアメリカ国籍を持っています。3人とも出産後の育休を取らないで仕事を継続しました。しかし私は小児科の臨床をバリバリ継続していたわけではありません。1人目出産後は小児内分泌外来+実験、2人目はポスドクでしたので定時帰宅、3人目出産後1年して8年ぶりに当直に入りました(若手ドクターが心配そうに!しばらく待機してくれていました)。子供達はベビーシッター、保育園、ファミリーサポート、ときに両方の実家(遠方です)、といったたくさんの親以外の人たちに育ててもらいました。子育ては終わりがなく、特に成長してからのほうが個々の人格も確立してきますので、かなりのエネルギーを使います。赤ちゃん時代には「ここを過ぎれば楽になる〜」と思っていたのですが。私のアメリカでの最初のボス(Professor Cecilia Giulivi, ミトコンドリア研究の権威です)昨年日本に特別講演のために来日しました。彼女はワーキングマザーで2人のお嬢さんがいます。彼女は留学時はチョー怖いボスでしたので、私は随分泣かされたのですが、久しぶりの再会では、家族のこと研究のことをゆっくり話すことができました。私が家でPC開けて仕事をしていると話すと「家で仕事したら、だめよ!子供と向き合わなければ〜。」とお説教されました。私が彼女のラボで働いていたとき、彼女は朝5時にオフィスに来て、夕方5時には絶対に帰宅していました。ランチはパンをかじってコーヒーをすすりながら論文書いていましたっけ。
最後に
今回このような執筆の機会をいただきましたことを心より感謝いたします。
アメリカでの2人目のボスの言葉です。Do you realize how lucky you are for this opportunity to pursue higher education, to work in this lab, and to contribute something to science? 新型コロナ感染症の拡大による緊急事態宣言が出された中でこの原稿を書いています。未曾有の事態のなかで漠然とした不安と緊張感が続いています。自分も医療人のひとりであることに誇りを持って、この状況のなか毅然とすごしたいものです。 -
Vol.2
鳴海 覚志(なるみ さとし)
所属:国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部 基礎内分泌研究室長自己紹介:
2001年に慶應義塾大学医学部を卒業し、その後の2年間は主に慶大病院小児科で臨床研修を行いました。川崎市立川崎病院(小児科)で2年間勤務した後、医師5年目の時に大学に戻り、小児内分泌代謝グループの一員となりました。時を同じくして大学院に入学し、先天性内分泌疾患の分子メカニズムに関する研究を始めました。このようにして最初の4年間はどっぷり臨床、次の4年間はどっぷり研究という生活を経験し、9年目以降は「自分がよりフィットしていた方に進もう!」と考えていました。結果として研究を続ける進路を選び、現在まで約15年にわたり、先天性内分泌疾患の分子メカニズムに関する研究を行っています。小児内分泌診療は好きですしやりがいも大きかったのですが、グループ内には非常に有能な先輩が何人もおり、「世界一の小児内分泌科医を目指すのは難しいかも・・・」と率直に思いました。一方で小児内分泌学研究はというと、そもそも担い手が少ないこともあり、世界一を目指す上でのチャンスが広がります。また、大学院生時代に行った研究が国際的にも評価されていたこともあり、「粘り強く続ければいずれ世界の小児内分泌学に貢献できるかな・・・」というようなビジョンを描けるようになりました。2016年まで慶大小児科に在籍した後、国立成育医療研究センター研究所・分子内分泌研究部へと移籍しました。現在はチームリーダーとして若い小児内分泌科医たちとともに小児内分泌学研究に没頭する日々を過ごしています。
恩師3人は小児内分泌科医
小児科には循環器、呼吸器、腎臓、新生児・・・など10種類を超える専門分野があります。その中で小児内分泌学を選んだ理由について書いてみたいと思います。時は医学部生だった頃にさかのぼります。一連の医学部講義の中で特に内分泌学に興味を持ち、学生が主体的に作る講義録のうち「内分泌学」シリーズの編集を担当するなど積極的に勉強しました。内分泌学は血液中をめぐるホルモンを中心とした学問ですが、このホルモンという物質がとにかく凄いのです。ホルモンは血液中に低濃度にしか存在しないのですが(オリンピックプールにスプーン一杯分くらい)、血中濃度が通常の半分になっても倍になっても、劇的な症状が出現します。昔から暗記が最小限で済むシンプルな科目が好きだった私は、内分泌学こそが最もシンプルな医学領域と感じました。内分泌学ではホルモンの作用の把握が大切であり、内分泌疾患といえばホルモン作用の増強(甲状腺機能亢進症など)か減弱(甲状腺機能低下症など)が主体です。ホルモン作用の基本知識から、病態や臨床症状のあり方が論理的に引き出せることに美しさを感じました。このように学生時代から内分泌学が気になる存在であったため、小児科医になってからもほどなく内分泌代謝グループがサブスペシャリティの候補になりました。とはいえ、小児科医人生を左右する決定とも言えますので、決断を下す前には迷いもありました。最終的に決め手となった要因は、医師としての修行時代に遭遇した3人の「すごい先輩」がいずれも小児内分泌科医だったことでした。
第一の恩師は研修医時代に国立霞ヶ浦病院(当時)で3か月間お世話になった七尾謙二先生です。一般小児科診療の枠内においても内分泌学の考え方が有効であることを、急性胃腸炎で尿中ケトン体が検出されたお子さんを例にとるなどして丁寧に教えていただきました。小児内分泌学が、成長ホルモン欠損症に代表される特徴的な稀少疾患ばかりを対象とする分野ではないことを教わりました。第二の恩師は川崎市立川崎病院で2年間ご指導いただいた長秀男先生です。内分泌専門医である長先生の外来には多数の小児内分泌疾患患者さんが通院していました。当時、電子カルテが導入されたばかりということもあり、「カルテ入力を手伝いますね!」などと理由をつけては外来を見学し、一緒に診察をさせていただきました。甲状腺ホルモン不応症の患者の検査入院を担当した際には、長先生の指令で白昼堂々と大学に出張し、内分泌代謝グループの先輩に教えていただきながら自らの手でPCR-シーケンスを行い、遺伝子診断を行いました。現在では日本中の小児内分泌疾患患者さんの遺伝子診断に関わっていますが、あの原体験が大きなきっかけとなりました。第三の恩師は大学にいても離れてもつながりのあった長谷川奉延先生です。長谷川先生は優れた小児内分泌科医・小児内分泌学研究者であると同時に卓越した教師兼プロデューサーでもあり、私のサブスペシャリティ選択に決定的な役割を果たしました。そして、内分泌代謝グループに入った後にも、長谷川先生の指導力の恩恵を最大限に受けることになりました。長谷川先生は研究に集中できる環境を整えてくださっただけでなく、私が考えたちょっとした着想や工夫を大切にして下さり、「だめもと」でも新しいことや難しいことに恐れずに挑戦することを許して下さりました。大学には大学院生時代と特任助教時代をあわせて11年間在籍しましたが、まさに人生の収穫期と言える実りの多い期間でした。この間に20本くらいの英文論文を書きました。

2008年当時の慶大小児科内分泌代謝グループ。中央が長谷川奉延先生。
筆者(ダークグレーのシャツ)の後方に座っているのが七尾謙二先生
2008年の米国内分泌学会での筆者(左)と長谷川奉延先生(右)
小児内分泌学研究の魅力についての私見
小児内分泌学研究の魅力についてひとこと述べたいと思います。小児内分泌学の特徴として、対象疾患の豊富さ、多彩さが挙げられます。視床下部・下垂体の疾患、甲状腺疾患、カルシウム代謝疾患、糖尿病・低血糖症、性分化疾患、骨系統疾患など様々なホルモン産生臓器、関連臓器の疾患を扱いますし、低身長症や染色体異常症といった臓器の定まらない疾患も対象としています。体中をめぐるさまざまなホルモンの作用や病態をマスターする必要があり、それだけでも飽きることはありません。患者さんを治療する上で様々な種類のホルモン製剤をあやつることになりますが、これらは効いたのか効いていないのかがわかりにくい風邪薬と違って劇的な有効性があります。
研究的側面からみると、小児内分泌領域の内分泌疾患(ホルモン産生臓器の異常)は先天的な異常(先天性内分泌疾患)が中心です。これらの疾患の根本原因の主体をなすものは、臓器の発生・分化過程の異常や生理作用発揮機構の異常です。これは臓器への過負荷、破壊(腫瘍圧迫、自己免疫機序など)、加齢性変化を主な原因とする成人内分泌学とは大きく異なる点です。先天性内分泌疾患の基盤には遺伝子レベルの変化が存在する事例も多く、先端技術を用いた遺伝学的研究を実践できる分野ともなっています。これらの背景から、ひとりひとりの小児内分泌疾患患者さんを丁寧にみてゆくことが、ホルモン産生臓器の発生、分化、生理作用発揮機構の分子レベルでの理解へ自然に通じていきます。また、現代医療ではただ単に診断にたどりつくだけでなく、患者さんをより精密な細分類へとグループ分けし、個別要因を考慮したベストフィットな診療を行う「プレシジョン医療」の考え方が広がりを見せています。小児内分泌学では「プレシジョン医療」の概念が提唱されるはるか以前から、患者さんの状態を分子レベルで理解しようとする文化が築かれていたと言えそうです。
残念ながら現時点では良い治療法がない「難病」に該当する小児内分泌疾患も存在します。このような患者さんの希望となるような新しい治療法を開発する上でも、病態を分子レベルで理解することが不可欠です。1920年代のインスリン発見からすみやかな臨床応用の事例に代表されるように、内分泌学は分子をキーワードとした治療展開に可能性が開かれています。「ひとりひとりの患者さんを大切にし、精緻な診療を実践したい」というタイプの医師、医学研究者が大いに活躍できる分野だと思います。分子を基盤とした病態理解や治療に関心のある方、自らの可能性を小児内分泌学というフィールドで試してみたい方、内分泌疾患への探究心を世界の子どもたちのために役立てたいという志に燃えている方・・・ぜひ日本小児内分泌学会の門を叩いていただければと思います。
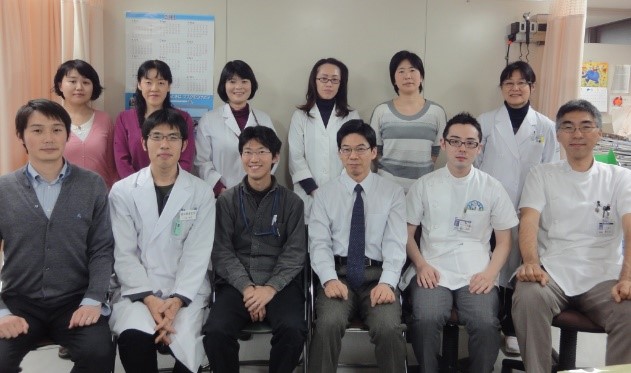
2012年当時の慶大小児科内分泌代謝グループ
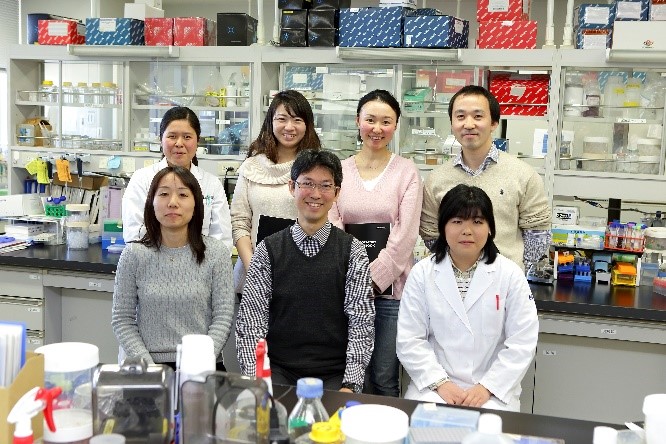
国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部・鳴海チーム。中央が筆者
-
Vol.1
山本 幸代(やまもと ゆきよ)
所属:産業医科大学 医学部 医学教育担当教員 准教授自己紹介:
山口大学医学部卒業後、産業医科大学小児科に入局。大学院では、生理学教室でオレキシン、NPYなどの摂食関連ペプチドの研究を行いました。学位取得後メリーランド大学、イリノイ大学シカゴ校に留学し、視床下部での遺伝子発現調節に関する研究をしました。今も細々ですが、後輩の先生方と摂食関連ペプチドの生後発達機構に関する研究も続けています。
現在学内では医学教育を担当しており、臨床診断学やOSCEなど卒前の臨床教育に携わっています。自分自身も勉強し直すことが多いですが、学生と一緒に純粋に学ぶ喜びを感じることもある日々です。最近の医学部教育では人間性教育のため様々な新しいカリキュラムが取り入れられています。人間性という課題はハードルが高すぎますが、学生たちの真摯に学ぶ姿勢をみると、私自身も初心に戻る気持ちになりやりがいを感じるときもあります。
小児科での専門診療と臨床研究は継続しており、小児肥満・メタボリックシンドロームや糖尿病に関する臨床研究をしています。我々の教室はサイトカイン解析を行っているので、他グループと共同してヘパトカイン、マイオカイン分泌動態の解析も行っています。学校検尿での尿糖陽性者のβ細胞機能評価にも取り組んでいます。
最近は市や県など地域の学校保健関係の委員会に参加させていただく機会が増えました。学校や教育委員会など立場が違うと意見が異なる場合も多いですが、それぞれの立場と役割をお互いに理解した活動の重要性を感じます。平成29年度からは九州学校検診協議会の成長発達・小児生活習慣病委員会の委員長をさせていただいています。九州全体の実態調査を行い、九州沖縄地区全体として統一したマニュアル作成やシステム導入などを目指した活動をしています。なかなか浸透しない現実にぶつかることも多いですが、その分やりがいがあると解釈してめげずに継続したいと思います。第2回 日本小児内分泌学会 九州沖縄地方会の開催を担当して
平成31年2月23日に 第2回日本小児内分泌学会 九州・沖縄地方会を担当させていただきました。本会は、地域での小児内分泌学の発展を目的に、日本小児内分泌学会最初の地方会として立ちあげられ、第1回は、井原健二先生(大分大学小児科学教授)が開催されました。一般演題では、貴重な症例の報告、地域での新しい取り組みの紹介、九州全体での臨床研究の提案など、多岐にわたる演題が発表されました。参加者は76名(教育講演講師の大薗恵一先生、伊藤善也先生のほか、理事の長谷川行洋先生、藤原幾磨先生を含む)で、若手からベテランまで各世代の交えての活発な討論は大変有意義であったと思います。若手医師の育成が地方会の重要なテーマの一つですが、中堅以上の先生方もたくさん刺激を受けていたようです。若手の先生同士の交流も活発になり、所属や立場を超えお互いに良い影響を与える機会になったと思います。



学会の様子と事務局を担当してくださった先生方
メッセージ
私が小児内分泌学会に最初に参加したのはまだ内分泌グループに所属する前の3年目の時で、病棟で担当したACTH不応症の兄妹例を発表し、Endocrine Journalにも報告したのが最初の論文です。その後も貴重な症例や研究結果を発表する度に、専門診療に携わる姿勢、学会や論文でその集積を発表する意義など多くのことを学びました。参加される先生方の熱心で真摯な姿勢を感じ、先輩方の姿を見て励まされることが多いです。我々のグループは、大学を離れた後もグループの指導を続けてくださる河田先生、医局を離れてもアドバイスをいただく機会が多い朝山先生や土橋先生の他、川越、久保、荒木、後藤、斉藤、桑村、多久、池上、島本と、多くの後輩が所属するグループになりました。指導することばかりではなく後輩から教わることも多く、先輩だからと気負うことなく、年齢や立場を超えて相談し助けあえることが大事だと感じます。同じグループだけでは、内分泌の魅力を十分に伝えきれませんが、後輩たちも、私と同じように学会に参加し、発表をとおして、多くのことを学んでいると感じます。
今回このような執筆の機会をいただいたことで、改めてこれまでとこれからのことを考えることができました。小児内分泌医の育成を、学会全体で支援しようという精神を忘れずに、後輩の先生方と共に学んでいきたいと思います。
内分泌グループの先生方と一緒に(昇進祝いをしていただいたときの記念写真)
